資産運用・資産管理と切っても切れない関係にある税制・節税について
制度関連
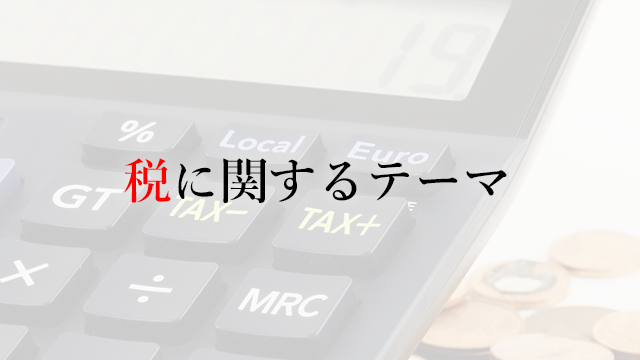 制度関連
制度関連 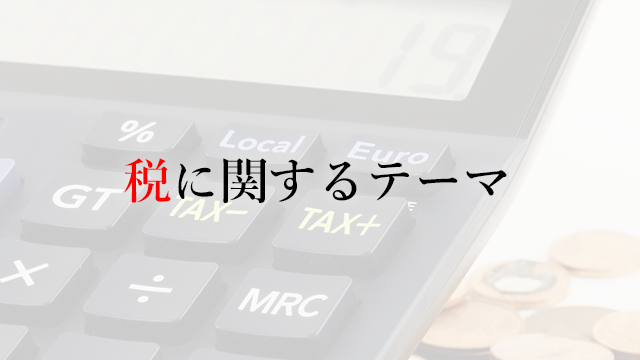 制度関連
制度関連 資産運用・資産管理と切っても切れない関係にある税制・節税について
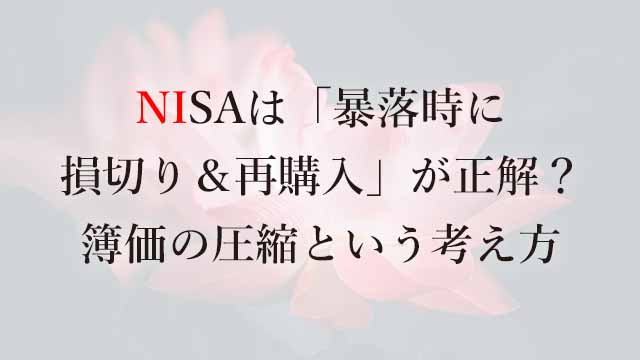 NISA・つみたてNISA
NISA・つみたてNISA 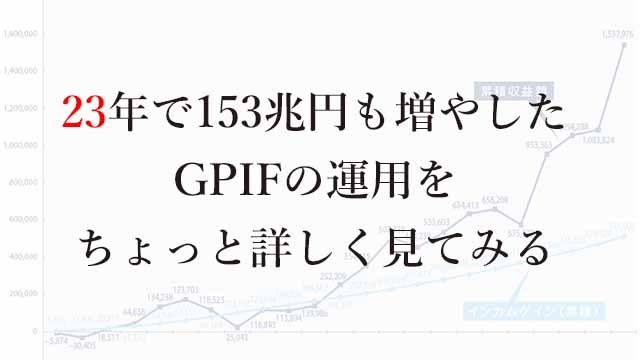 年金制度
年金制度 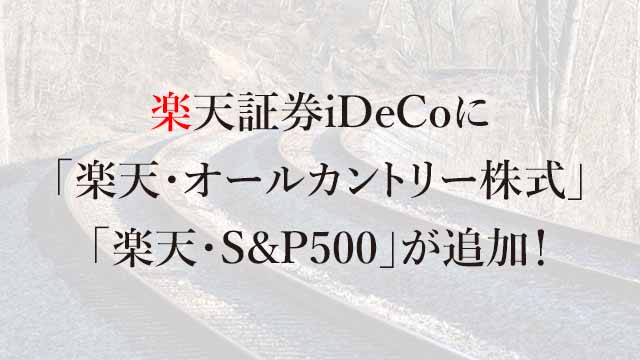 iDeCo
iDeCo 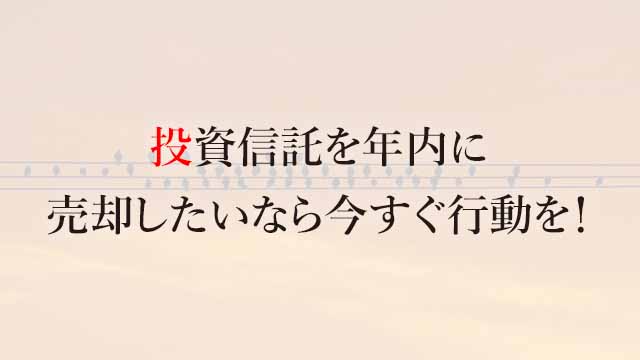 NISA・つみたてNISA
NISA・つみたてNISA 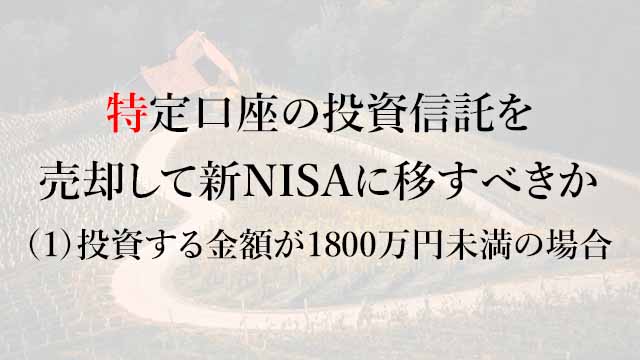 NISA・つみたてNISA
NISA・つみたてNISA 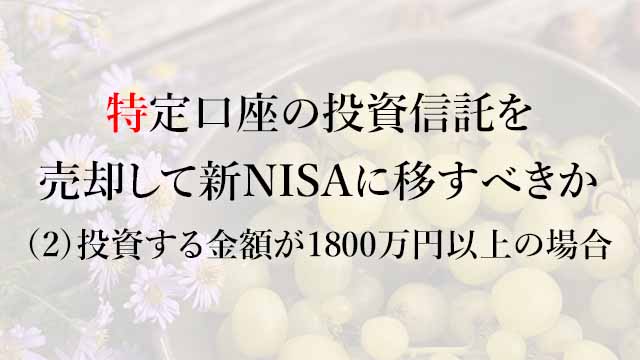 NISA・つみたてNISA
NISA・つみたてNISA  NISA・つみたてNISA
NISA・つみたてNISA 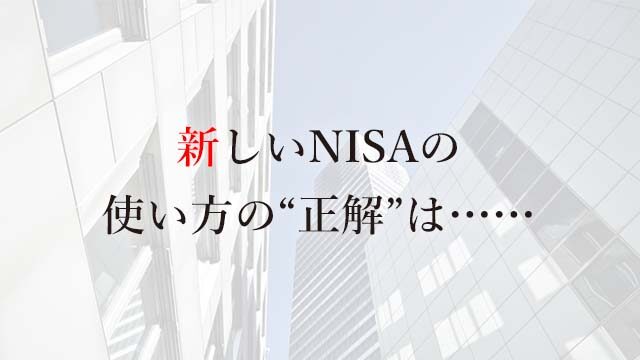 NISA・つみたてNISA
NISA・つみたてNISA 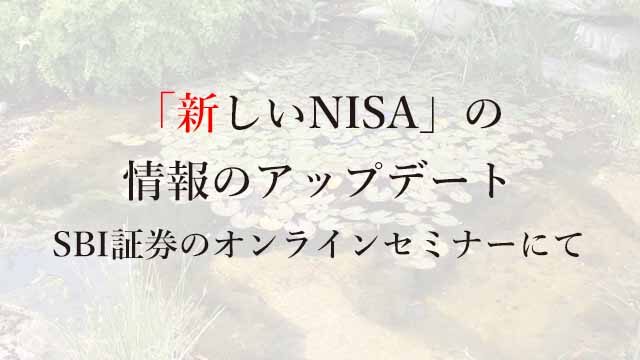 NISA・つみたてNISA
NISA・つみたてNISA  NISA・つみたてNISA
NISA・つみたてNISA